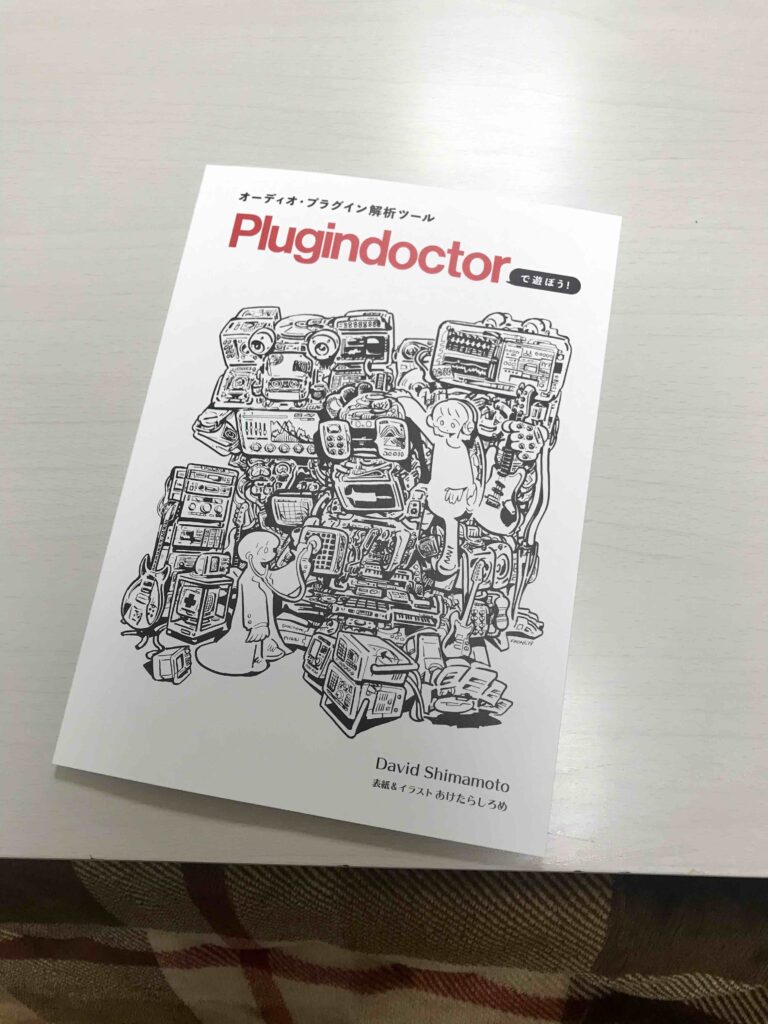あつまれどうぶつの森のメインテーマであるところの、みんなあつまれ(海外ではWelcome Horizonsというタイトル)をremixしました。
発売前から CM やらの動画で聞いて、いいなーと思っていて、なんだか耐えられず作りました。
けけハウスと、アーバンけけもすごくお気に入りなので、なんかやりたいところです。勢いがついたらやります。
3DS で発売された前作、とびだせどうぶつの森もそうだったのですが、あつまれどうぶつの森では一貫して感じににルビが振ってあります。
なので、一部難しい表現や知らないことがゲームの中で色々起こるのでサポートが必要な場面はあるものの、まだ5歳の娘も自分で遊ぶことができるので、ここ最近は自分よりも遥かに長い時間娘のほうがどうぶつの森を遊んでいます。
おかげで、ひらがなを随分すらすらと読めるようになったり、数字が読めるようになったり、ゲーム内の動物が言っていることを理解できるようになったりとできることがどんどん増えてきています。このままお金の計算や、色んなものをいい感じに配置するためのマスの計算やらできるようになってくれると良いなぁ。と思います。
ゲーム規制条例がどうだとか最近ありますが、我が家ではこんな感じなので、ゲームが悪いとはどうしても思えなかったりします。
ゲームの中とはいえ色んな経験を積んでいるなーという感じがします。
子供は物理的に体を動かすことも大切ですが、色んな情報がコンピュータ上のデータとして記録されたり、それにソフトウェアを通じてアクセスする世の中にもなってきているので、そういった考え方にゲームを通して慣れていくってのも、むしろ教育の一環としてむしろ必要なんじゃないかとすら思うこの頃です。
少し話が変わりますが、ここ最近のコロナの影響で、娘が通っていた運動教室が、一箇所に集まって従来通りに行うことのリスクが高いということで、zoom を使ってのオンライン運動教室になりました。
なんか、運動教室をオンラインでって本当にできるのか?って思っていたのですが、とりあえず1回やっていたのを横からちょろっと眺めた範囲では、ちゃんと成立していたのでびっくりしました。
よく考えたら親戚とLINEでビデオ通話とか日頃からやってるわけだし、こういうのには子供のほうが慣れたりしているのかもしれないなーって思いました。
ゲームも含め、いい感じにテクノロジーを活用して過ごしていきたいですよね、と思いました。